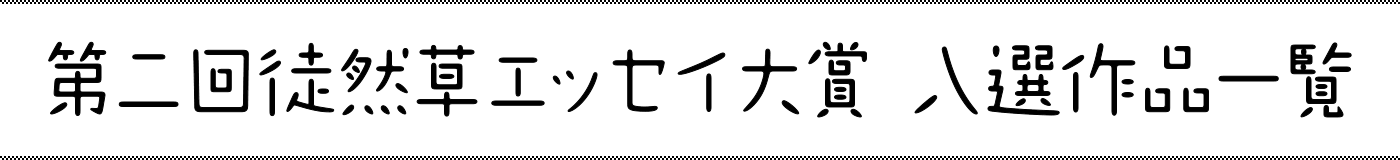
20年前の冬晴れの午後、結婚を控えた私は母親に手伝ってもらいながら、引っ越しの準備をしていた。次々に想い出の品々が出てきて、その中の1つに、亡くなった祖母の形見である着物があった。
私は形見分けの時に、あえて使い物になりそうにない着物をいただいた。その着物は、亡くなる前日まで祖母が着ていたものだった。
親戚は、指輪や財布など、実用的な物や、それなりに資産価値がありそうな物を選んでいた。私は、その時は恥ずかしくて、なにも言わなかったが、祖母のにおいがいっぱい詰まった着物が欲しかった。だから、あえて亡くなる前日まで着ていた普段着を選んだのだ。
寂しくなった時に、こっそり祖母の着物のにおいをかいで、懐かしもうと考えたのだった。
しかし、実際はたんすの肥やしになってしまい、手元に出して懐かしむようなことは一度もなかったような気がする。心のお守りだったのかもしれない。
久しぶりに、祖母の着物を手にして、私は両手に抱えて、そーっと顔を埋めてみた。
緊張しながら静かに息を吸い込むと、懐かしいにおいが私を包んでくれた。確かに祖母のにおいがした。
「ねえ、お母さん、まだおばあちゃんのにおいがするよ」
私は興奮して母に叫んでしまった。
「あんたは、おばあちゃんのことが本当に好きだったもんね」
と母が遠くを見るようなしぐさをしながら言った。
祖母の懐かしいにおいに浸っていると、20年前の出来事が思い出された。
祖母の所に遊びに行くと、祖母はよくおはぎを作って私達をもてなしてくれた。祖母の作るおはぎは、この上なく美味しくて、大好きだった。ある日、親戚が祖母の所に大勢集まった時に、祖母はいつもよりも、たくさんおはぎを作ってくれた。私は、おはぎに手を伸ばし、口に入れた。しかし、その時のおはぎは、ちょっとしょっぱかった。
親戚が、「うわー、ばあちゃん、このおはぎ、しょっぱいよ」と言って口から出してしまった。
それを見た祖母が慌てて口に入れると、
「ごめん、ごめん、砂糖と塩を間違えた」
と言いながら、お皿ごと全てのおはぎを下げてしまった。祖母は、
「お前はしょっぱくなかったのか?」
と言いながら、優しくシワシワの両手で私を抱きしめてくれた。
「うん、もう一つの味がした」
とだけ私が言うと祖母は、
「お前は優しい子だね」
と目に涙を浮かべながら、さらに強く抱きしめてくれた。
私はその時のぬくもりと、祖母のにおいを今でもはっきり覚えている。祖母から頂いた形見の着物には、まるで祖母がそこにいるかのように、未だにあの時のにおいがしっかりと残っていた。形見の着物のお陰で、20年以上前の祖母との大切な思い出が蘇ってきた。
「今度はこの着物どうする?」
母が形見の着物を引っ越し先に持って行くかどうかを聞いてきた。結婚という新しい生活を前にして、そろそろ捨てなさい、という気持ちを込めて言ったように私は感じた。
母は自分の母親を息子が孫として愛する気持ちを喜びながらも、新しい生活にこのまま引きずっていくことを、心配しての一言だと私は理解した。私は親離れならぬ、祖母離れをすべく、着物を置いていくことを決意した。ただ、せっかくここまで大切にとってきた形見を捨ててしまうのには抵抗が少なからずあった。何か他のものに作り変えてもらえないか、私は母に相談した。
一ヶ月後、結婚式は無事に終わり、披露宴の最後に、花束贈呈のシーンがあった。
私が、新しい両親に花束を渡している横で、かみさん(新婦)が、私の母から紙袋をもらっていた。
その時はわからなかったが、あとで見てみると、それは祖母の形見の着物が生まれ変わった巾着袋だった。母は私の頼みを聞いてくれたのだった。
披露宴が全て終わり、新居となる家に着いてから、かみさんに、巾着袋の説明をするとかみさんは私に共感してくれたのか、泣きだした。
私が祖母を思う気持ちをかみさんと分かち合えたような気がして、私はとても嬉しくなった。
すると、私の目からも涙がこぼれてきた。私の結婚に対する不安が解消され旅立つことができた瞬間だった。