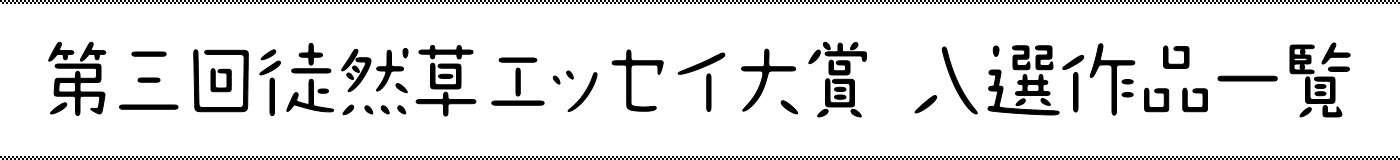
私は五歳でピアノを習い始めた。一人目、二人目の先生には短い期間教わっただけで、九歳のとき引っ越した町の、近所の若い女の先生に、長くお世話になることになった。
その先生とのレッスン初日、前の先生のもとで練習していた曲を上機嫌で披露すると、先生は「指の力が弱いわね。まずきちんと音を出すところから始めましょう」と、ピアノを習い始めた子が最初に与えられるような本を差し出した。猛烈な怒りで頭がカッと熱くなったが、黙って受け取り家へ駆け戻った。
翌日から仕方なく、それを練習し始めた。母が「どうしたの!? そんな小さな子が弾くような曲を弾いて」と飛んできたが、「ほっといて」と追い返す。学校では友達が「ベートーベンのソナタ、むつかしくて困っちゃう」やら「メンデルスゾーンの無言歌集ってきれいな曲がいっぱいあるのよ」などと話すのを、歯をくいしばって聞き流した。
その本をやっと終えたら次は練習曲をやり直すことになり、友達との差は開くばかり。たまらずレッスンをやめたいと母に言うと、「あなたがやりたいと言ったのに、中途半端なまま投げだすの?」とけんもほろろだ。
そんな憂鬱な毎日に転機が訪れたのは、十四歳の秋のこと。ある日先生の家を訪ねると、前の人が長引いているらしく何やら曲が聞こえていた。じゃまをしないようそっと部屋に入り、隅の椅子に腰かけて待つ。上体をたっぷり使って弾いているのは大学生らしき女性だ。その音に耳をすませているうちに、ふと何かが頬にふれた。指でさわって驚く。涙だ。私は泣いている! なぜ? そう、この曲があんまり美しくて……何かやさしい透き通ったもので胸がいっぱいになってしまったのだ。
女性が帰り、先生と二人になったとたん、「今の曲はなんていう曲ですか!? 私、弾いてみたい!」と叫んでいた。先生は驚き顔で「ショパンのノクターン遺作よ。でもあなたにはまだちょっと難しいから……同じショパンのワルツをやってみない?」と尋ねた。「でもまだ練習曲が——」と言いかけると、「もちろん練習曲も続けながらよ。でもずいぶん指の力がついたから、そろそろいろんな曲を始めようと思っていたの」と先生はにっこり笑った。
その日からがぜん、レッスンが楽しくなった。いつかあの曲を弾きたい。目標ができた私にさらに力を与えてくれたのは、他ならぬ自分の指だ。しぶしぶながら続けてきた基本練習は、確かに私の指を鍛え上げてくれ、いつのまにか望む音を、望む強さで、出せるようになっていたのだ。
気がつけば毎日、一時間、時には二時間以上ピアノに向かうようになった。こちらが一生懸命練習すれば、音はそれと同じ、いやそれ以上のものを返してくれる。そんな私の姿に先生の指導にも熱が入り、十七歳の発表会でついにあの曲を弾くことになった。
本番が近づいたある日、プログラムの下刷りを見せてもらい驚いた。なんと私の名前がいちばん下にあったのだ。最後に弾くのは、教室で最も上手な人と決まっている。「私、無理です」と泣きそうな顔で振り返ると、先生は微笑んだ。「今のあなたなら、大丈夫」。
発表会当日、第一部、第二部と順調に進み、いよいよ最後の部が始まった。舞台の袖で、緊張に息が苦しくなりながら出番を待つ。いよいよ名前が呼ばれ出て行こうとしたとき、先生がそばにきて、ぎゅっと手を握ってくれた。「さあ、楽しんでらっしゃい」。
その声に押されるように舞台へ出た。一瞬まぶしすぎてくらくらする。ピアノの前の椅子に座ると、大きく息を吐きながら自分へと言い聞かせた。今の私なら、大丈夫。
ライトの光を受け輝いている鍵盤へとそっと指をのせる。ショパンのノクターン遺作。あの日のかたくなだった心をとかしてくれた美しく、何より大切な曲を、せいいっぱいの力で弾ききろう。誰かの心へ届くように。
演奏を終えて袖へ戻ると「すばらしい演奏でした。うちの娘もいつかこんな風に弾けるようになるのかな」とアナウンス担当の男性が、感極まったように声をかけてくれた。教室の仲間たちもみんな手を叩いてくれている。
その中に、誰よりも見たかった人の笑顔を見つけた。走りよると先生は涙声でささやいた。「ありがとう。ピアノを続けてくれて」。私の声も涙でにじんだ。「私こそありがとうございます! ピアノのすばらしさに気づかせてくださって」。それは先生と私の心が、ピアノを通じてしっかりと結ばれた日だった。
その後、社会人になったのを機にレッスンをやめたが、今もピアノはかたわらにあり、ときどき大好きな曲を弾いている。あの大切な思い出の曲、ショパンのノクターン遺作も。
そして実家へ帰るときは、いつも少し遠回りして先生の家の前を通る。「ピアノ教室」の白い看板がかかっているのを見て安心し、今日も誰かのレッスンの音が聞こえてくるんじゃないかと、思わず耳をすませるのだ。