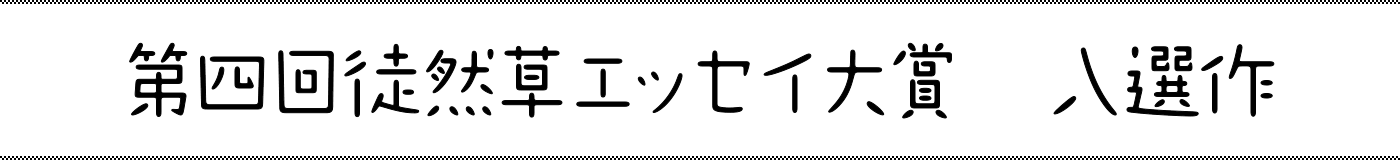
昭和三十年の秋、私が小学六年のとき、次兄が亡くなった。生まれつき心臓が弱かった次兄は心臓麻痺を起こしたのである。
村では人が亡くなると火葬場で
荼毘に付した。火葬場は村はずれの山の麓にあり、木造建てで屋根からは長い煙突が突き出ていた。
火葬する人のことを村では隠亡焼と呼んでいた。隠亡焼は別の集落に住んでいる五十過ぎの男だった。大人たちのなかには、「オンボヤキ、オンボヤキ」と蔑んで呼ぶものもいた。子供たちはそれを真似て同じように蔑むのだった。私もそのなかのひとりだった。
次兄は末っ子の私をなにかと可愛がってくれた。私もそんな兄のことが大好きだったので、涙がつぎつぎとあふれて泣きじゃくった。
次兄の葬式が終わると、荷車にその棺をのせて草の茂った野良道を父と長兄が火葬場まで運んだ。一面の田んぼには黄金色の稲穂が風にゆれていた。母と一緒に私も荷車の後ろをついていった。火葬場に着くと、麻の上っ張りに股引、腰には荒縄をしめた隠亡焼が準備を整えて待っていた。私は隠亡焼をどことなく蔑んだ気持ちで見た。火葬場の中にはいると、遺灰の残り香がつんと鼻をついた。中央には頑丈そうな火葬炉があり、人を容易に寄せつけぬ威厳のようなものを感じさせた。
「本日はお世話になりますが、よろしく頼みますけん」
父と母が隠亡焼に頭をさげた。
「なぁに、これはわしの仕事じゃけん」
隠亡焼は照れくさそうに短く刈ったごま塩頭に手をやった。
隠亡焼の指示で父と兄が棺を炉の台車に載せた。そのあと隠亡焼が台車を炉の中に押し込み、扉をガシャンを閉めた。そのとき私ははっとなった。これでもう二度と兄の人間としての姿を見ることはなくなるのだ。人の命の儚さ、運命の非情さを強く感じた。みんなが帰るときになって、私は残ることを父母に告げた。私をことのほか可愛がってくれた次兄を最後まで見送りたいという思いからだった。
お骨拾いの時間を父が確認しみんなが帰ると、隠亡焼は薪を炉の中に入れ、火をつけた。
「嫌な臭いがするのでみなすぐに帰るのに、坊はひとり残るとは感心じゃの、まぁ、ここに座れや」
私は隠亡焼と並んで薪の束に腰をおろした。やがて炉の中で薪がゴォ、ゴォと音を立てはじめた。そしてしばらくしたときだった。
「ゴトン」と炉の中から不気味な音がした。私はびくっとなり、「いまの音はなに? もしかして兄ちゃんが生き返ったんじゃないの」
隠亡焼にすぐさま問いただした。
「驚いたか。あれはの、硬直していた体が熱にあぶられ、曲がって棺桶にあたった音じゃ。いわば兄ちゃんがこの世との最後の別れを告げたのよ。なんまんだぶ、なんまんだぶ」
隠亡焼が炉に向かって両手をあわせた。私もあわてて同じようにした。
そのあと、隠亡焼が歌を口ずさみだした。
♪人はみないつかは死んで灰となる
あの世に極楽あれど地獄もある
みな極楽に行きたいと思うなれど
それはわからぬ、仏様のみぞ知る
しかし、あんたは極楽に行ける。極楽じゃ、極楽じゃ、
人はみないつかは死んで灰となる、なんまんだぶ、なんまんだぶ♪
まるで御詠歌のようだった。顔に深い皺を新たに刻むようにもう一度静かに歌った。
死人はこのようにして隠亡焼からあの世へと送られていくのか。これまで隠亡焼をどことなく蔑んだ目でみていた自分が恥ずかしくなった。隠亡焼にたいする思いが一変した。尊敬の念がしだいに湧き上がってきて、そっと隠亡焼の横顔を見た。するとその顔はまるで崇高な仏様のように見えた。そのとき、
「これからは死人と溶け合い、一体となっていく時間なのじゃ。おまえもわしと一緒に歌を歌い死人をあの世へとおくってやるのじゃ。なんまんだぶ。なんまんだぶ」
隠亡焼はそう言うと、またさきほどの歌を口ずさみはじめた。私はその後につづいた。
炉の中では今まさに兄ちゃんが焼けており、その嫌な臭いは充満している。しかしこれは兄ちゃんが私に別れを告げている臭いなのだ、そう思って必死に耐えた。
私は息抜きに一時外に出た。長い煙突からはもくもくと白い煙が立ち昇っていた。
ああ、兄ちゃんは今まさに天国へと昇っているのだな、そう思った。