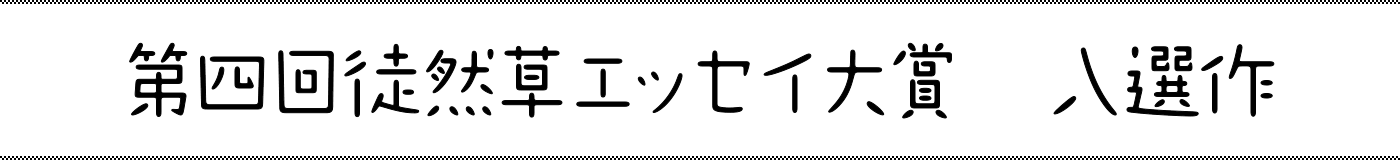
未来の私が彼女を思い出すのは、いつだろうか。
私が以前に住んでいた団地の一階には、私の事を「あーちゃん」と呼んでくれる濱田のおばあちゃんという人が住んでいた。彼女は本当の孫ではないが私の事を孫といってくれる人で、背が低く、眼鏡をかけていて、家の中にチリひとつないくらいのキレイ好きで、私に会うと必ず挨拶してくれるとても優しい人だった。私が幼い頃はよく、私の住んでいる3階までのぼってきて、膝の上にのせてくれたり、お菓子をくれたりしたのだが、少し時が経つと、用があるときは、彼女から電話がかかってきて、私が1階に下るようになった。しかし、私が幼稚園の年長の時の冬、彼女は入院してしまった。
がんだった。彼女の体をむしばんでいたそれは、もうどうにかできるものではなくなっていて、彼女の余命はそう長くはなかった。わたしは休日に何度かお見舞いに行き、真っ白な病室で、彼女の手をにぎりしめて、彼女の話を聞いた。彼女の手は小さかった。彼女はお見舞いに行くたびにずっと「家から見える桜が見たい。だから早く家に帰りたい」と言っていた。その時の私は、その言葉をどう聞いていたのだろうか。彼女は桜を見る前に亡くなってしまった。
彼女がよく言っていた「桜が見たい」という言葉を、私は今でもしっかりと覚えている。だけど、彼女がどんな声で話していたのか、どんな顔をしていたのかは、もう忘れてしまった。この文章も母に彼女がどんな人だったか思い出をたずね、少しずつ記憶をたどって書いたのだ。
私が大好きだった彼女を忘れたのは、私が薄情な人間だからだろうか。それとも、自然と忘れていくものなのだろうか。私にはわからない。ただ、いまでも私は彼女との思い出話を聞くと目頭が熱くなり、もっとしっかり彼女の声や顔を見ていれば、いや、視ていればよかったと後悔する。
私は変化が怖い。「何故」と問われると返答に困ってしまうが、分かりやすく言えば、時が経てば忘れる変化が怖い。私が濱田のおばあちゃんを忘れてしまったように、他の人もいつかは彼女を忘れてしまう。
――濱田のおばあちゃんがもう一度死んでしまう。そう思うと怖くて怖くてたまらない。私がこの文章を書こうと思ったのは、彼女の事も私が彼女を想っていた気持ちも、時の流れの変化で忘れないためだ。これからの私は濱田のおばあちゃんの事をまた忘れていくのだろう。だけど、私は彼女の事を忘れたくないのでこの文章を書き残しておくことにした。いつか、未来の私がこの文章を見つけて、濱田のおばあちゃんが生きていた事を思いだすのを願って。