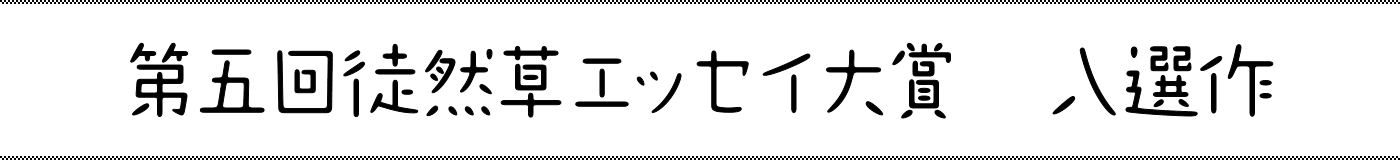
薬局から飛び出して、溜息交じりに空を仰いだ。
いつのまにか、灰色の雲が垂れ込め、小雨がパラパラ降っている。むずかる娘を必死にあやしながら診察を待ち続けて、二時間以上も経ってしまった。
(もう少し早く帰れると思ったんだけどな……。本降りになる前に、急がなくっちゃ)
娘の頭に抱っこ紐のフードカバーをすっぽり被せて、勢いよく駅前のバス停に走った。あいにく、長い列がずらりと伸びている。
すると、目の前の小柄な女性が、男子高校生たちにつめてもらえるよう声をかけてくださった。
「わざわざ、すいません。助かります」
屋根の下に入ることができて、ほっとひと息。ポケットからハンカチを取り出して、娘のあんよをすばやく拭いた。うす桃色の花びらがしっとりと雨に濡れて、やさしく揺れている。
(あっ、百日紅だ。フリルみたいで、かわいいな)
うっとり見とれているところに、バスがやってきた。混雑した車内に乗り込むと、今度は恰幅のいいサラリーマンが席を譲ってくれた。
「ここ、どうぞ」
「ありがとうございます」
すかさずお辞儀してから、かぶりを振った。
(ダメダメ、濡れた服で座ったら、あとの人が困るもの)
そう思って丁寧に断ろうとした矢先、ビニール袋がさっと敷かれた。空席の横に座る白髪のおばあさんが心を読んだように、鞄から取り出してくれたのだ。
「これで大丈夫よ。座ってちょうだいな」
「は、はい」
軽く会釈して腰を下ろすと、爽やかな音がシャカシャカ鳴った。
「あら、赤ちゃんのほっぺ、まっ赤ね」
「風邪を引いてしまって……。小児科で診てもらった帰りなんです」
「雨の中、大変だこと。ご苦労さま。早くよくなるといいわね」
おばあさんは心配そうに言うと、ワイン色の雨具を羽織って、バスからゆったり降りていった。
激しい雨が、窓にザンザン叩きつける。娘の泣き声が、わんわん泣きわめく。
「だいじょうぶ、もうすぐ着くからね」
背中をさすりながら、再びフードをつけた。いよいよ次だ。アナウンスが流れ出して、降車ボタンが光った。
先ほどバス待ちのときに前にいた男子高校生たちが立ちあがって、ぞろぞろ降りる。私もあわてて後に続いた。
「よし、ダッシュするぞ」
ぐっと気を引き締めて、黒く濡れたアスファルトに足をつけた。そのとたん、頭上にぱっと空が広がった。
「よかったら、どうぞ」
こんがり日焼けした笑顔が、キラキラまぶしい。
「いや、でも……」
「だいじょうぶです。家にビニ傘あまってるし、入れてもらうんで」
熱い眼差しに応えるようにこくりと頷いて、力強く差し出された傘の柄をぎゅっとつかんだ。少年がはにかむように短い髪をくしゃっと掻いて、友達の元に駆け寄る。
「どうもありがとう」
にこやかに四度目のお礼を口にして、お腹の底からぽかぽかしてくる。
「おだいじに!」
ほがらかな声が、ぴたりとそろった。部活バッグを揺らしながら遠ざかっていく仲良し四人組を見送って、ほっこりした気分で前を向いた。
そら色のビニール傘を、クルクル回す。思いやりの輪が、ルクルク踊る。
(わあ、きれーい)
パサッと広げるたび、冷たい雨粒がポンポン弾ける。うっぷんも憂いも、タンタン弾け飛ぶ。
「みてみて、バスだ。バスがきたよー」
「ゆっくり、順番に乗ろうね」
「うん!」
傘をすぼめて、娘と手をつないでステップをのぼる。きっちりひと席ずつ間隔を開けて、静かに座る。
流れる景色は、あのころといっしょ。きっと、マスクの下の柔らかい微笑みだって――。
換気のために数センチほど開いた窓から、ほんのり甘い香りが漂ってくる。息をのむほど美しい、満開の百日紅だ。
あゝ、あたたかい出会いに満ち溢れたバス時間が、ひどく恋しい。