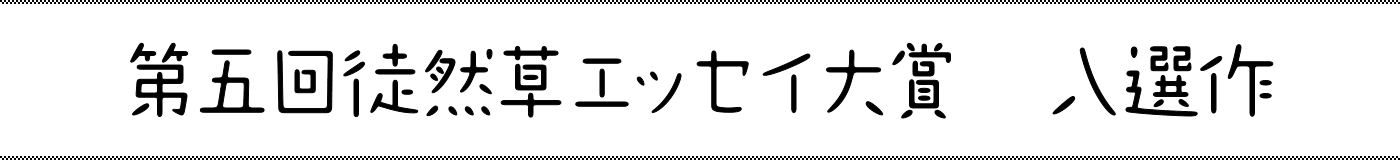
一九八三年、当時三歳だった私をひとりで育てていた母は、通っていた保育園の前の掲示板に張り紙を貼った。そこには「毎日仕事が終わるまで娘を預かってくれる人を募集する」という内容が記されていた。昭和の空気は今よりずっと大らかだったのかもしれないが、少しギョッとするような行動だ。しかしそれを見て名乗りを上げてくれたのが、アライさんのおじいちゃんとおばあちゃんだった。
おじいちゃんはすでに仕事を引退して、多くの時間を家で過ごしていた。おばあちゃんはキリスト教系の大学に勤めていた。
ふたりが住んでいた家は小さな木造の平屋で、トイレは汲み取り式、お風呂は外にあったのだが、当時周囲にそのような家はもうほとんどなかったような気がする。ずいぶん後にここを訪れた時、今にも壊れてしまいそうだなと少し笑ってしまったほどの古い日本家屋だった。
おじいちゃんは毎日自転車で、私を保育園まで迎えに来てくれた。自転車のサドルは、雨に濡れてもいいようにいつもスーパーの袋で覆われていて、車体はおじいちゃんがペダルを漕ぐたびに、ギイ、ギイとなった。
家に着くとおじいちゃんはまず、勝手口の窓から夕陽が差し込む小さな台所に立ち、夕飯を作ってくれた。特に私が好きだったのはチャーハンだ。ピンクのかまぼこが甘く、玉ねぎがシャクシャクとした歯触りでとても美味しかった。
おじいちゃんのつけたたくあんも私の好物で、母が帰り際によく「あっちゃんこれが大好きだから」と言われては、お土産に持たせてもらっていた。
ご飯を食べ終わる頃になると、シスター姿のおばあちゃんが仕事から帰ってくるので、その後はみんなでくつろいで過ごした。私はウィスキーを飲むおじいちゃんの膝の上で、昭和歌謡が流れる歌番組を見ながら、おじいちゃんが解説する「美空ひばりの歌い方」について学んだりした。
母の残業でお泊まりをした日には、私が寝付くまでおばあちゃんが子守唄を歌ってくれた。さらに夜更けになると、庭から鈴虫や蛙の鳴き声がうるさいほど聴こえたのだが、それらの音に負けないくらいの大音量でおじいちゃんのいびきもうるさかったので、私はよく眠っているおじいちゃんをわざと起こしてはトイレについてきてもらった。
夏は三人で縁日に出かけた。その時に着た紺地に白い朝顔が描かれた浴衣は、おばあちゃんが縫ってくれたものだった。
小学校に入学する前の年には、おじいちゃんが自分の名前を漢字で書けるようにと少しづつ字を教えてくれた。
そのようにして私は幼少期の毎日を、あの小さな古い家でのんびりと大切に過ごした。
小学校に入学した後は、段々とおじいちゃんの家に行くことが減っていった。中学生になると塾や部活や友達づきあいが始まり、高校生になるとアルバイトで毎日が忙しくなった。
それでもおじいちゃんは、毎年欠かさず私の誕生日とクリスマスには、スーパーの袋のかかった自転車に乗って、ケーキとたくあんを届けに来てくれた。
おじいちゃんが亡くなったと連絡がきたのは、私が高校一年生の時だった。
おじいちゃんのお葬式で、母も私も人目もはばからずに泣いた。誰かが、
「あのおじいさんずいぶん気難しい人だったのに、血も繋がってないのにあんなに泣く人がいるなんて驚いた」
と言っていた。おじいちゃんは夜中だってトイレについて来てくれたんだよ、と私は心の中で思った。
今、おじいちゃんとおばあちゃんの家があったところは駐車場になっている。私はあの頃の母の歳を超え、仕事をしたり子育てをしたりしながら、あの日々が、あのように自然に成り立っていたことに、改めて少し驚いたりもする。でもきっとそれは、凹凸がピタリと重なり合うように、全員が素直な心のままで自然に導かれ合っていただけの話だったのかもしれない、と言うと少し格好つけすぎだろうか。
ただとにかく私は時々、すりガラスの引き戸の前でタバコを吸うおじいちゃんの姿をぼんやりと思い出しては、あの小さくて古い世界を、空に掲げたいほど愛おしく、そして誇らしく思うのだった。